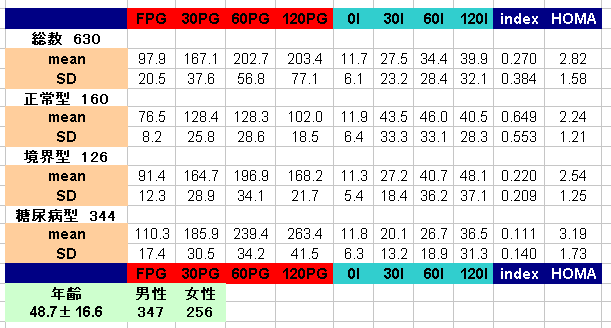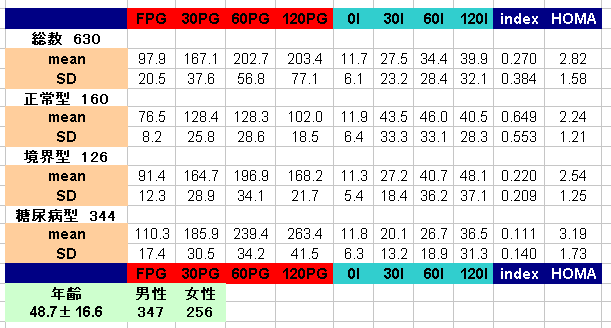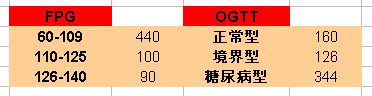|
一般的な検診における糖尿病スクリーニングには,空腹時血糖(FPG)とHbA1cを用いることが多い。日本人ではグルコース負荷に対するインスリン分泌能の低下が軽症のうちから認められるため,75g糖負荷試験(GTT)を施行すると,FPGが110 mg/dl未満でも2時間値(2hPG)が200 mg/dl以上であるものが少なくない。FPGが正常範囲内で2hPGが144〜199 mg/dlの群に虚血性心疾患の発生が多いとの報告もある。
またHbA1cは2hPGよりもFPGとの相関が強く,FPGが上昇している糖尿病患者の血糖動向の把握には有用だが,食後過血糖を中心とした軽症耐糖能障害患者のスクリーニングには不向きである。
広島原爆障害対策協議会・健康管理センターの伊藤千賀子先生は,本年の糖尿病学会において以下のように説明している。すなわち,「GTT判定別にHbA1c値の度数分布をみると,正常型ではHbA1c値が5.0%をpeakとする正規分布を示し,境界型のHbA1cが5.0〜5.3%の範囲で高率となり,正常型に比してやや幅広く分布し,正常型との重なりも極めて多かった。糖尿病型の分布はさらにpeakが低く右方へ偏位し,半数以上が境界型や正常型と重なっていた」。これらから,「HbA1cをGTTの代わりに糖尿病診断に用いることには慎重を要する」と結論している。
したがって現状の検診では少なからぬ食後過血糖型糖尿病患者を見落としていることになる。それゆえしばしば日本人の糖尿病診断にはGTTの施行が推奨されるのだが,一般の検診においては対象者を2時間安静のもと拘束する困難さと費用の問題で,あるいは頻回な採血など検査施行者側の煩雑な手間が理由でGTTを完遂するのはむずかしい場合が多い。
そこで,短時間で検査を終了するためGTTにおける0分および30分の血糖値(FPG,30PG)とインスリン値(0IRI,30IRI;実際には耐糖能障害の程度の判定にきわめて重要なinsulnogenic-indes(index))を用いて,ないし費用対効果を重視してFPGと60分の血糖値(60PG)で,おもに食後過血糖型耐糖能障害を早期発見・スクリーニングする方法を検討した。
既報の頻回採血75g糖負荷試験被検者(Keio J Med 47: 28-36, 1998)のうち,FPGが60以上140未満の630人のデータを無作為に抽出した。630人の被検者は,FPG60以上110未満が440人,110以上126未満が100人,126以上140未満が90人であるが,これを日本糖尿学会のGTT判定基準によって分類すると,正常型160人,境界型126人,糖尿病型344人となる。すなわちこの630人をFPGのみで判断すると344人の糖尿病型被検者の70%以上が見落とされることになる。
著者注:今日一般に信じられている糖尿病有病率を鑑みると,このデータは耐糖能障害のある群へ偏りがあろうことが推測される。(この偏りを客観的に証明しうる疫学調査も存在しない。)
しかしFPGで110-125の被検者が2hPGが200を超える割合(94/100,ちなみに60-109の者は159/440)を素直に解釈すれば,検診においてGTTを敢えて推奨せず,欧米人の基準と同値のFPG126mg/dl以上を糖尿病型としている現在の診断基準には問題があるといわざるを得ない。 |